現代の経済環境は急速に変化しており、企業は柔軟な対応を求められています。
直近ではアメリカのトランプ大統領が打ち出す関税政策などが世界規模の不安定要素を提供していますし、他国が絡む地政学的リスクも増大し続けています。
国内でもビジネスに直結する不確実性が増している感が強く、経営者としては不安感が否めない状況です。
本章では世界経済の動向や経済成長、インフレ、金融政策、地政学的リスク、またトランプ関税の影響などについて、多角的に考察してみたいと思います。
トランプ流関税政策の影響

まずは最新事情としてアメリカトランプ政権が強行する関税政策について改めて押さえておきます。
そもそもトランプ関税とは一体何なのかということですが、これはアメリカ国内産業の保護を目的としたものです。
日本には24%の関税が課せられることになり、我が国の経済政策全般に強い衝撃をもたらす結果となりました。
トランプ氏が大統領就任時に石破首相が訪米し良好な関係を演出できた印象がありましたが、そこはやはり筋金入りのビジネスマンで、トランプ氏は日本を特別視せずに一律関税を実施してきました。
現在、国会周辺では報復関税をちらつかせたうえで交渉を行うべきとの論調があるようですが、日本が反対措置として取れる手段は限られているうえに、仮に実施したとしてもアメリカ、及びトランプ氏個人にとっては痛くもかゆくもないでしょう。
結果として対立を生むだけなので筆者個人としては報復関税は取るべきではないと考えますし、政府内の主要な政治家や外務、財務方面の実務担当者もそのように見ているとの報道が聞かれます。
日本としてはアメリカから輸入する電化製品の安全性のハードルを下げて輸入を増やすなどの譲歩が可能ということで、弱いながらもこうした論点をまとめてパッケージにして交渉材料とするしかないでしょう。
なお関税は中国、メキシコ、カナダ、EUに対して特に厳しい措置が取られています。
関税の導入によってアメリカ国内の製造業は一定の保護を受ける形となるものの、様々な方面に影響が波及すると考えられ、インフレ逆行などのリスクを叫ぶ専門家も多くいます。
今後、輸入品価格の上昇がアメリカの企業と消費者に大きな影響を及ぼすことになる予想ですので、この動きをキャッチアップしていく必要があるでしょう。
トランプ関税について世界貿易と我が国経済の二方面での影響をまとめてみます。
①世界貿易への影響
過日、トランプ関税の導入に反発し中国は報復関税を発表し、これに呼応してトランプ氏はさらに関税率を倍増させる警告を出しています。
米中貿易摩擦が激化することが予想され、その結果世界のサプライチェーンが混乱して製品価格が上昇する恐れがあります。
特に電子部品や自動車、食品、農産物の流通に今後どのような影響がでてくるか注視が必要です。
②日本企業への影響
日本企業は輸出を中心とした製造業が強い影響を受けると考えられます。
米国向けの自動車や電子機器の輸出には関税負担が増加するため、多くの企業は生産拠点の分散化やサプライチェーンの見直しを求められます。
影響が強い業種、業界に対して国は経済支援の準備を整えている最中で、日本政策金融公庫などを通して金融の融通策を導入する運びです。
通常は売り上げが落ち込んだ後の事後的救済となる施策を、売り上げの落ち込みが予想される段階で事前的に資金注入を図れる算段で新制度の準備が進められています。
世界経済の動向
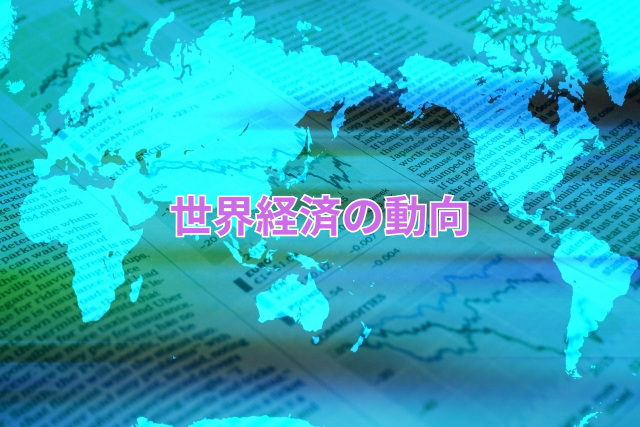
次に全体的な世界経済の動向ですが、こちらは経済成長率の鈍化がみられます。
IMFの予測によれば世界経済の成長率は2025年以降も低成長が続く見込みです。
米国や欧州は経済回復の兆しを見せていますが、中国やその他の新興市場の成長率は鈍化しています。
特に中国経済の減速は世界市場に大きな影響を与えています。
世界的なインフレは一時的にピークを過ぎたものの、食品やエネルギー価格の高騰が続いており、企業のコスト構造に影響を及ぼしています。
企業は価格戦略の見直しやコスト削減策の導入が求められるでしょう。
各国の中央銀行は金利政策を調整しており、企業の資金調達環境に変化が生じています。
我が国のように金利が上昇する国では企業は借入コストの増加となるので、資金調達戦略の見直しが求められます。
地政学的リスクの影響

ロシア・ウクライナ戦争は、当初トランプ氏の介入で落ち着きが持てる期待があったものの、実際には一時的な停戦もままならない状況が続いています。
力技で何とかしてしまうのではとの期待があった分、中途半端な状況に落胆の声も聞かれます。
いずれにしてもこの戦争に由来する不安要素は払しょくできておらず、エネルギー価格や食料供給の不安定要因は完全には取り除かれていません。
エネルギー価格の高騰で企業のコスト負担が増加していることは国民の足元の経済でも如実に実感できます。
企業の運営コストにしめるエネルギー価格の占有率は依然として経営者の悩みとなっています。
我が国の周辺では台湾問題が存在し、年々中国と台湾の衝突リスクは増していると判断できます。
台湾情勢の緊張は半導体市場にも影響を及ぼしています。
世界の半導体生産の中心である台湾へのリスクが高まることで、電子機器の供給が不安定になる可能性があります。
日本経済の現状

我が国の国内事情に目を向けてみましょう。
日本では30年ぶりの賃上げが進んでいるところ、一方で構造的な人手不足も続いており、企業は労働力の確保と生産性向上の両立を図る必要に迫られています。
円安については引き続き注視が必要です。
トランプショックの影響で一時的に円高ドル安の状況も見られたものの、根本的なものではなく、なお円安の状況が続いています。
円安は輸出企業にとっては追い風となる一方で、輸入企業にはコスト増加の圧力となります。
日本企業は為替リスクを管理して適切な価格戦略を講じる必要があるでしょう。
プラスの材料としてはDXの進展がみられる点が挙げられます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速することで、企業では業務の効率化や新たなビジネスモデルの構築が進められています。
またAIの導入が進み、企業の業務効率化が図られています。
製造業、物流、マーケティング分野ではAI活用が急速に進み、在庫管理の自動化などが鋭意進められています
クラウド技術の活用も進められていて、データ管理や業務プロセスの最適化が実現しています。
サプライチェーン戦略の変化
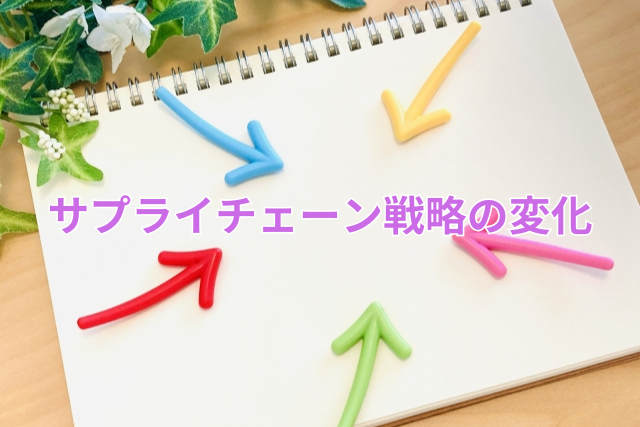
企業は地政学的リスクや関税の影響を受けないようにするために、調達先を多様化する動きをみせています。
中国からの輸入を減らし、東南アジアへのシフトを考える企業も多いと思われます。
サプライチェーンと在庫管理は切り離して考えることはできません。
仕入から製品製造、販売と在庫管理は一貫して管理する必要があります。
原材料価格の変動に対応するため、多くの企業が在庫管理の見直しを進めています。
適切な在庫管理によってコスト削減を図り、供給の安定化を目指すことになります。
持続可能な経営の重要性

我が国を含め世界の潮流を見ると環境・社会・ESGへの投資が拡大しており、企業は持続可能な経営を求められています。
特にCO₂排出量の削減やサステナブルな製品開発が重要視されています。
企業は国際的なSDGs目標を考慮し、ビジネス戦略に組み込む必要に迫られていると言って良いでしょう。
これをプラス要素として取り組むことが成功への糸口になりそうです。
環境負荷の低減や社会貢献を進めることで、ブランド価値を向上させることが可能になります。
まとめ
この回では世界経済の動向について多角的に見てきました。
最新の経済トレンドは企業経営に多くの影響を与えています。
特にトランプ関税は目下の注目の的で、この影響がどのように波及するか注視していく必要があります。
しばらくはこの方面のニュースに注目ですね。






