人手不足問題は以前は運送業や宿泊業などで目立っていましたが、現在はほぼ全ての業種で人手不足感が感じられる時代になっています。
人材の採用活動においては、他社で成功した例を参考にすることで良い変化を生むことが期待できます。
この回では経済産業省がまとめた採用活動の成功例からいくつかピックアップして、①採用活動を工夫したきっかけ、②実際に取り組んだ内容や仕組み、③取り組んだ後どうなったかという3点にフォーカスしてまとめていきたいと思います。
業種業態によってヒントになるものがあればぜひ参考になさってください。
■株式会社あけぼの通商 住宅用ガラス販売
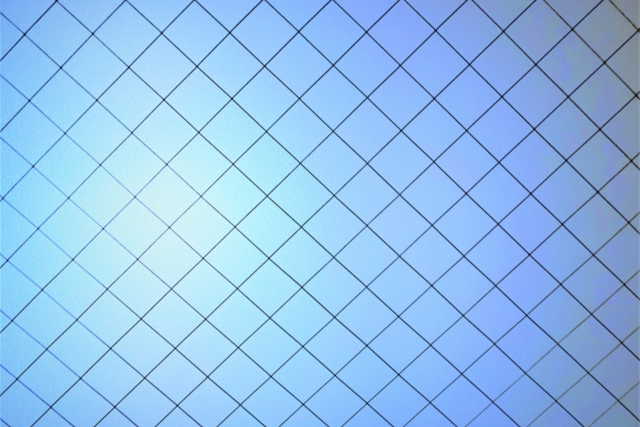
①きっかけ
・自社ビルを建てた2000年頃の構想で、女性が安心して活躍できる職場をつくりたいと考えていた。
・世の中では生活が便利になっている実感がある一方、生活費が増えて夫だけの収入では苦しい世帯が多い実態がある。女性が活躍できる会社づくりを意識することに。
②取り組んだ内容や仕組み
・子育て中の女性を事務職に積極的に採用。
・短時間勤務を導入し家庭との両立を支援。
・子育てが終了したタイミングで本人が希望すれば正社員に登用。
・有給休暇は1時間単位で取得できるようにした。
・子どもの病気や学校行事がある時は数時間だけの「中抜け」もできるようにした。
・確定拠出年金制度を導入し、退職金制度を充実させて退職後の不安を払拭した。
③取組後どうなった?
・女性社員の定着が進み、子育て終了後も戦力として活躍してくれている。
・出産、育児休業を取得した女性社員のほとんどが職場に戻ってくれた。
・人事評価制度を明確にしたことで性別不問で対等に仕事ができる環境になり、社員のモチベーションが上がった。
■旭電子株式会社 製造業

①きっかけ
・細かな手作業が多い生産過程で女性の従業員は主戦力であった。
・専門知識を持つ女性社員の確保に不安を覚えていた。
②取り組んだ内容や仕組み
・一日に一つ、女性社員に専門知識を身に着けてもらうワンポイントレッスンを施行。
・女性社員のスキル、ノウハウ向上の仕組みを構築。
・短時間勤務制度の導入。
・育児休業中の社員に随時情報提供を行い、つながりを維持。
・育児休業を取得する社員の代替要員の確保。
・女性社員が使いやすいフレックスタイム制、半日休暇、誕生日休暇、ノー残業デーなどの導入。
・力が必要な作業については機械化を促進し、省力化を実現した。
・熟練者と未熟練者を組み合わせて技術の伝承がしやすい環境を構築。
③取組後どうなった?
・女性が男性と同等に働くのが当たり前の社風が形成された。
・教育制度で昇進した女性4名が管理職に登用された。
・対外的にも女性が働きやすい会社という評判が広まった。
■株式会社アラタナ 情報通信

①きっかけ
・地方のIT企業は業界間の繋がりが薄く都心よりも不利を感じていた。
・若手社員が自身のスキル向上に不安を感じていた。
②取り組んだ内容や仕組み
・企業間留学制度の導入
・社内公募と選考を重ね、意識の高い社員が外部企業に留学し、成長できる機会を確保した。
・留学中は日報や週報などで活動内容を報告させ、本人にも成長を実感してもらう工夫をした。
・終了後には自社と留学先企業の双方に課題や改善方法のプレゼンを実施。
③取組後どうなった?
・外の世界で得た気づきや新たな視点を持てるようになり、自社のメンバーに好影響をもたらした。
・まるで転職したかのような大きな変化を実感でき、社員自身のキャリアアップにつながった。
・東京の同業他社の実際を体験することで自分や自社の不足している部分に目が行くようになり、またこれを克服することで自信につながった。
■有限会社有吉農園 青果卸売業

①きっかけ
・若い正社員登用に苦戦していた。
・長期間安定して働いてくれる社員が不足気味であった。
・きついイメージが強く応募しても集まらない。
・業種的に春~秋にかけての人手不足感が強い。
②取り組んだ内容や仕組み
・時間のあるシニア層に目を向けて採用活動を開始。
・午前と午後それぞれ4時間の短時間シフト勤務を導入。
・子育て中の女性社員は急な休みを取りやすいようにし、短時間勤務制を導入。
・シニア層には口頭でなく書面でマニュアルや作業内容を配布。
・記憶力に自信がないシニア層にはグラム数などの数字を覚えやすいように指示面で工夫した。
・重量物は作業台を使いやすいものに変えて負担を軽減した。
③取組後どうなった?
・主婦やシニア層10名の採用に成功。
・口コミが広がり地域の評判もよく、仕事の発注も増えた。
・シニア層は仕事時間の区切りを2時間にするのが生産面で都合が良いという発見があった。
・作業内容を紙で指示することでミスが減った。
■株式会社いせん 旅館業
①きっかけ
・慢性的な人手不足。
・お客様へのおもてなしを提供するためにも従業員が無理なく働ける環境が必須と感じた。
②取り組んだ内容や仕組み
・業務の見直しと多能工化。
・旅館業以外に飲食や物販、旅行、製造など多角経営を行っていることから、これらの業種で適性のある仕事を選べるように工夫した。
・リーダー研修やメンター制度の導入などの教育体制を構築した。
・キャリアアッププログラムを導入し社員が興味のある分野をさらに引き延ばせるように工夫した。
・地域貢献を意識して地場産の素材や商品をお客様に提供した。
③取組後どうなった?
・従業員数は10年で3倍に増えた。
・多能工化の成功で従業員の働き方や勤務体系の幅が広がった。

■ウインナック株式会社 製造業
①きっかけ
・自治体からの要請で障害者の採用に取り組んだが定着が悪くすぐ辞めてしまう。
・健常者社員もすぐ辞めてしまい技術の伝承がままならない。
②取り組んだ内容や仕組み
・人を大切にする組織作りを目指し「社員課」と創設。
・社員の立場に立って苦情や意見を言える環境を構築すると同時に、福利厚生を充実させる。
・障害者支援として手話通訳者や障害者相談員の配置を実施。
・生活面の指導や支援体制を取り入れて仕事と私生活両面で安心できる環境を構築した。
③取組後どうなった?
・安心して働ける環境が整い、障害者、健常者双方で定着率が向上した。
・定着率が上がり社員のスキルが上がったため製品の信頼度も上がる好循環が生まれた。
・スキルアップにより社員の自信が大きく向上した。
・スキルを身に着けた社員が他の社員に指導できるようになり、生産性が向上した。
・企業のイメージアップ効果で仕事の引き合いも増えた。
■株式会社潮技術コンサルタント 技術サービス業
①きっかけ
・55歳以上の従業員が全体の30.4%を占め、高齢化が心配になる。
・熟練者の退職で技術の伝承ができないと企業の存続が危ぶまれる事態に。
②取り組んだ内容や仕組み
・定年後の継続雇用は年齢制限なしで働けるようにした。
・熟練者と若手社員がペアになって仕事を組み、指導助言を行えるようにした。
・空調や照明を配慮して高齢者が働きやすい環境にした。
・希望すれば短時間勤務を可能にした。
③取組後どうなった?
・ベテラン社員が必ず同行することで顧客からの信頼を得られるようになった。
・熟練者の技術やノウハウが若手社員に引き継がれることで、ベテラン社員側もやりがいを持てるようになった。
■宇都宮工業株式会社 金属プレス業
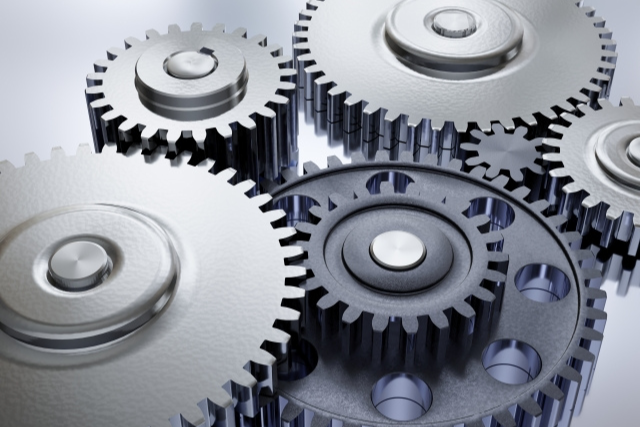
①きっかけ
・新規事業進出を機に新たな人材確保に苦慮することに。
・新卒工学部系の人材が必要であるところ、採用方法が分からず困っていた。
・製造ライン稼働のために相当の頭数が必要になった。
②取り組んだ内容や仕組み
・新卒人材の採用では若いアイデアやデザインが世の中に出ていく魅力を積極的に発信。
・製造ラインでは女性社員を戦力として積極的に採用し、そのために残業を避けたい社員などの要望を細かくヒアリングした。
・社員には自らの改善意識を持たせるための仕組みを導入。成長に対しては賞金を支給し、モチベーションと生産性の向上を図る。
③取組後どうなった?
・自らの改善運動は成果を発揮し、様々な部門で生産性が向上、売り上げの伸びにつながった。
・開発営業などの人材確保に成功した。
・働きやすい会社であることが社員づてに広がり、夫婦や家族で入社する者も増えた。
■エイベックス株式会社 製造業
①きっかけ
・早期離職が相次ぎ入社10年未満の社員が9割を占める状態に。
・ベテラン層が少なく若手社員の教育が難しい状況になっていた。
・そのためさらに離職率が上がり深刻さが増していた。
・女性のパート社員も応募してもなかなか集まらず困っていた。
②取り組んだ内容や仕組み
・入社1年未満の社員には特別に手厚い教育体制を整備した。
・文理、国籍、男女を問わない採用方針に転換。
・産前産後休暇、育児休暇を取得しやすいようにし、復職については公共機関からの認定制度を取得してアピールした。
・長時間残業を防ぎ、多能工化を促進した。
・これまでフルタイムのみの募集であったが4時間から勤務できる募集枠を設置した。
③取組後どうなった?
・教育制度の導入により離職率が大幅に低下した。
・実際に現場で働く女性社員の声を発信することにより、女性の応募が増えた。
・子育て中の女性も短時間勤務の応募者が増えた。
■採用活動における注意点
以上、様々な業種での人手不足解消の取り組みを見てみました。
全体的に、今は売り手市場の時代ですから、企業側がかなり気を使わないと募集採用はままならない時代になっています。
しかし誰でもいいから取りあえず頭数を揃えるという姿勢は危険で、ミスマッチが起きると採用後のトラブルが懸念されます。
面接時には過度に自社をよく見せようとしない、事前に社内見学やインターンで仕事の実際を体験してもらうなど、丁寧な取り組みが求められます。
特に基幹人材の採用を考える場合は、早期離職による採用コスト面からも影響が大きいので、慎重に採用計画を練ることが大切です。
「人はすぐには集まらない」という前提で、余裕を持った採用活動に取り組んでください。
■まとめ
この回では人手不足解消を目指した各社の採用活動から成功例をいくつかピックアップしてみました。
業種業態によって必要な人材は異なるので、各社必要な人材確保に取り組んでおられることと思います。
全般に通じることは、社員が何を望むのか、どうすれば安心して働けるのか経営層が聞き取り、環境を整備する必要があるということです。
人口減少が進む中で簡単にはいかない問題ですが、時間をかけて取り組んでいきましょう。






