数字は好きでも嫌いでも、経営において避けて通れない存在です。
ただ、売上や利益といった「結果の数字」だけを見ていても、会社が強くなるわけではありません。結果はあくまで“最後に出てくる数字”であって、そこに至るまでの過程にこそ、経営判断のヒントが隠れています。
伸びる会社と、伸び悩む会社の差はどこで生まれるのか。
その答えの多くは、「現場の数字」をどれだけ把握できているかにあります。経営者が見るべきKPIは、決して難しいものではありません。むしろ、毎日の動きの中に自然と存在している数字ばかりです。
そして、KPIの選び方ひとつで、会社の成長スピードは驚くほど変わります。
数字を管理するためではなく、判断を“早く・正確に・迷わず”行うためのKPI。この記事では、経営者が押さえておきたい5つの指標を、考え方とともに整理していきます。
売上の“前段階”を見る力が経営を変える

企業の売上は、いくつかの数字が積み重なって生まれます。
問い合わせがあり、商談が生まれ、受注につながる。そしてその裏側には、現場の行動や判断があり、小さな積み重ねが結果を形づくっています。
にもかかわらず、結果だけで判断してしまう企業は少なくありません。
売上が落ちると「広告を増やそう」「人を増やそう」と反応しがちですが、本当に改善すべき場所はもっと手前にあります。
問い合わせ数なのか、商談化率なのか、リピート率なのか。どこが細くなっているかを見誤ると、改善策はすべてズレていきます。
KPIの役割は、この“前段階のどこが動いているか”を浮かび上がらせることにあります。
売上という結果は、途中の数字が積み上がって初めて成立します。もし結果だけを見て判断しているなら、会社は常に「後追いの経営」になり、スピードも精度も上がりません。
たとえば、問い合わせが増えているのに売上が伸びていない場合──
原因は成約率かもしれません。逆に商談数は十分なのに利益が伸びない場合は、単価や粗利率の管理に問題がある可能性があります。
売上を伸ばすコツは、売上を“追う”のではなく、売上を生み出す“源流の数字”を見ること。
その視点を持てるだけで、経営の安定感は格段に変わります。
会社の“弱点”はKPIに必ず表れる

企業は、何となくうまくいっている時より、伸び悩んでいる時のほうが数字に現れやすいものです。ただ、その“兆し”は売上や利益の数字に出てくる頃には、すでに状況が悪化しているケースが少なくありません。
本当に見るべきは、その手前にある“KPIの変化”です。
KPIは、会社の弱点がどこに潜んでいるかを最も早く教えてくれます。
たとえば、売上が横ばいでも
・問い合わせ数だけが少しずつ減っている
・商談数はあるのに成約率が落ちている
・新規客が増えているのにリピート率が低い
こうした小さな変化は、数字としては数%のズレでしかありません。
しかし、このズレこそが“経営の危険信号”です。
多くの企業は、売上や利益を見て「最近ちょっと悪い」と気づきますが、その頃には原因が複雑に絡み合い、改善に時間がかかります。
逆に、現場のKPIで弱点を早めに掴める企業は、問題が小さいうちに手を打てるため、業績の落ち込みを未然に防ぐ力が強くなります。
会社が伸びていく時も同じです。
良い兆しは売上よりも先にKPIに現れます。問い合わせが増えていたり、成約率が改善していたり、客単価が上がり始めていたり。KPIを見ていれば「どこをさらに伸ばすべきか」が明確になります。
弱点も強みも、KPIには必ずヒントがある。
これを押さえている企業は、迷わない経営ができるようになります。
すべてのKPIは“5つの数字”に集約される

KPIと聞くと、「業種によって違う」「会社ごとに合う指標がある」と思いがちですが、実はどのビジネスでも根本は同じです。
業種が違っても、ビジネスモデルが違っても、会社の成長に直結する数字は共通しており、その本質は“たった5つの指標”に集約されます。
この5つを押さえるだけで、経営の解像度は一気に上がり、改善点・伸ばす点・課題の根本が驚くほど分かりやすくなります。
企業ごとに名称は変わりますが、構造はどれも同じです。KPIを複雑に見せているのは、現場の状況や用語の違いであって、経営として見るべき数字は、どれもこの5つに戻ってきます。
たとえば──
問い合わせが増えなければ商談が生まれませんし、商談が増えなければ成約数が伸びません。
さらに、成約しても単価が低ければ利益は薄くなります。
そして、いくら売れてもリピートされなければ成長は続きません。つまり、会社の成長は「どこが強く、どこが弱いのか」を、この5つの数字から把握することでほぼ説明できるようになります。
売上という“結果の数字”はコントロールできませんが、この5つのKPIは“会社が直接動かせる数字”です。
だからこそ、ここを見て判断することが経営の質を決めていきます。
次の見出しでは、その5つのKPIをひとつずつ紐解き、どう判断し、どう経営に活かすのかを整理していきます。
経営者が押さえるべき5つのKPI
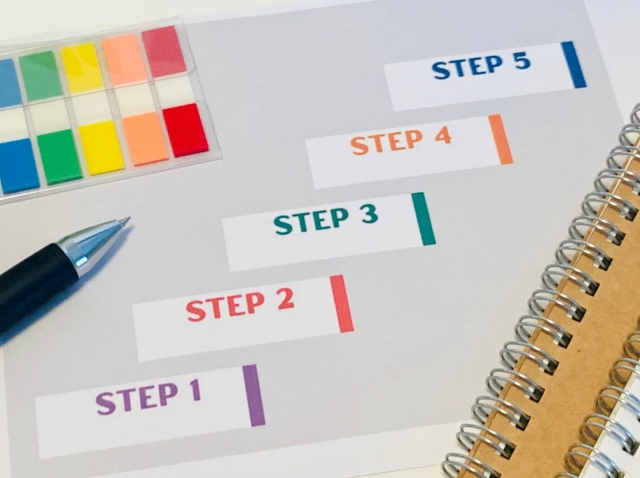
多くの企業でKPIがうまく機能しない理由は、「数字が多すぎる」「部門ごとに指標がバラバラ」「結局どれを見ればいいのか不明」といった状態が続いているからです。
しかし、経営の判断に本当に必要なKPIは、5つに絞ることができます。
この5つの数字だけ見れば、
・売上が伸びる理由
・利益が出ない理由
・改善すべき優先順位
・現場のどこが止まっているか
が瞬時に判断できます。
以下に、どんな業種でも使える“共通KPI”を整理していきます。
① 新規リード数(問い合わせ数)
会社の成長は「接点の数」で決まります。
どれだけ優れたサービスでも、知ってもらえなければゼロのままです。
新規リードの変化は、市場の動きや広告効果を最も早く示す数字であり、売上が伸びるか停滞するかは、この数字に最初の兆しが現れます。
・なぜ増えたのか
・なぜ減ったのか
・どの経路が最も効率的か
これらの判断はすべてこの数字から始まります。
② 商談化率(リードから商談へ進む割合)
問い合わせがあっても、商談に進まなければ機会損失になります。
商談化率は、マーケティングと営業の“つなぎ目”を示す数字であり、ここが弱い企業は成約数が伸びず、広告費だけが増えていきます。
商談化率が低い場合の主な原因は、
・初期対応の品質
・問い合わせ内容とサービスのズレ
・顧客層のミスマッチ
など、改善可能な要素ばかりです。
③ 成約率(商談から成約した割合)
営業の質を測る中心の数字です。
「商談数はあるのに売上が伸びない」という企業は、例外なくここに課題があります。
成約率を見ることで、営業の課題が明確になります。
・提案内容が刺さっていない
・比較されて価格競争になる
・顧客の課題把握が浅い
こうした問題は、数字の変化が必ず先に出ます。
④ 客単価(1件あたりの売上)
成約しても単価が低ければ、売上は伸びません。
逆に単価が高くなれば、商談数が同じでも利益は増えます。
客単価の変動は、市場の反応や価値の伝わり方に直結するため、「最近値引きが増えた」「単価の高い案件が減った」など、小さな兆しを見逃さずに改善点を見つけることができます。
⑤ リピート率(既存顧客の継続利用)
企業の強さは、新規よりも“継続”に表れます。
リピート率は売上の安定性を高め、広告費の依存を減らしてくれる数字です。
リピート率が低い企業は、
・顧客満足度が不安定
・サービス品質にムラがある
・購入後フォローが弱い
といった課題が潜んでいます。
逆にここが強い企業は、成長の基盤が極めて安定しています。
🔑 本章のまとめ
売上や利益といった「結果の数字」は、過去の積み重ねを表すものであり、これからの行動を教えてはくれません。
経営判断に必要なのは、結果が生まれる前に動く“現場の数字”を読み解くことです。新規リード、商談化率、成約率、客単価、リピート率。たった5つのKPIを押さえるだけで、会社の伸びる理由も、伸び悩む理由も、驚くほど明確になります。
経営者が見るべき数字は多くありません。迷いを減らし、判断の正確さを高めるために、今日からKPIを「会社の言語」として活用してみてください。






