景況DIの動きを見ると、2025年の市場は業種ごとの差が大きく、回復と停滞が同時に進む一年でした。数字の裏側を見ると、金利や物価、採用難といった外部要因が複雑に絡み、企業の景況感は揺れやすい状態が続いています。
こうした変化は、そのまま2026年の市場の方向性にも影響します。どの業界が伸び、どこに慎重さが必要なのか。景況DIの推移から読み取れるサインを手がかりに、来年の見通しと経営のポイントを整理していきます。
景況DIの推移が示す2025→2026の転換点

景況DIの推移を振り返ると、2025年の日本市場は「回復している業界」と「足踏みする業界」が同時に存在する、ゆがみのある一年だったことが見えてきます。とくに製造業と非製造業の差は大きく、景況感は一方向に揃わず、業界ごとに温度差が広がりました。
製造業では、円安や部材価格の落ち着きが追い風になる一方で、設備投資には慎重な姿勢が続きました。業績の数字だけを見ると改善している企業もありますが、「強く回復している」と言い切れるほどの勢いは感じにくい状況です。
非製造業では、外食・宿泊・インバウンドといった需要が堅調な反面、人手不足が深刻化し、現場への負荷が景況感を押し下げています。
業績そのものは良好でも、採用難や人件費の増加が経営の重しとなり、先行きへの見方は慎重にならざるを得ない場面が増えています。
2025年後半を通じて目立ったのは、“業界間の差が縮まらなかった”という点です。以前のように景況感が同じ方向へ戻る傾向は弱く、むしろ差が定着しつつある印象があります。この動きは、2026年の市場予測を考えるうえで重要なサインであり、「全体が良くなる・悪くなる」という読み方が通用しにくくなることを意味しています。
企業心理の揺れも見逃せません。
金利、為替、物価、人手不足といった複数の外部要因が同時に動いたことで、数字が改善しても慎重姿勢を崩さない企業、逆に数字が厳しくても攻めの投資を続ける企業が出てきています。こうした“期待値の揺れ”は景況DIにも表れており、投資姿勢の二極化が2026年にも影響しそうです。
景況DIは未来を断言する指標ではありませんが、変化の入口をとらえるうえでは非常に有効です。2025年の推移が示しているのは、一律の追い風や逆風ではなく、「動きやすい業界」と「踏ん張りが必要な業界」がはっきり分かれ始めているという事実です。この“ばらつき”こそが、2026年の市場を読み解く最初のポイントになります。
2026年に影響が出る主要テーマ

景況DIの動きから読み取れるのは、2026年の市場が単純な「好況・不況」の二択ではなく、複数のテーマが重なり合うことで業界ごとに異なる表情を見せる一年になるという点です。同じ外部環境でも、追い風に変わる企業と重荷になる企業があり、その差がより鮮明になりやすい状況にあります。
特に注目すべきテーマは、人手不足、物価や金利の水準、個人消費の動き、そして中小企業を中心に加速する省力化投資です。これらは単体で影響するのではなく、組み合わさることで企業の景況感に揺れを生みやすくなります。
以下に、2026年の市場で重要になるテーマを整理します。
【2026年 市場の主要テーマ】
| テーマ | 市場への影響 | 想定される企業側の動き |
|---|---|---|
| 人手不足・採用難 | 非製造業を中心に継続。人件費の増加が続く | 採用強化より定着率改善へシフト、業務効率の見直し |
| 物価・原材料費 | 上げ止まりつつも高水準が続く | 価格転嫁の早期判断、仕入れ条件の再交渉 |
| 金利の動き | 金利上昇局面が続く可能性 | 借入条件見直し、返済計画の再設計、資金調達手段の分散 |
| 個人消費の伸び鈍化 | 消費関連企業に影響が波及 | サービス価値の向上、客単価向上策、固定費の管理 |
| 省力化・効率化投資 | 中小企業でも投資意欲が高い | 自動化・DX導入、助成金活用、設備投資の選別 |
| 為替の変動 | 製造業と輸出企業には追い風、輸入企業には負担 | 価格戦略の調整、調達先の分散、為替リスクの管理 |
こうしたテーマは、2026年の市場の“基調”を形づくると同時に、企業の判断に直接影響します。とくに金利と採用難はコスト構造の変化につながるため、資金繰りや投資の優先順位をどう整理するかが問われる一年になります。
市場を見渡す際には、「自社がこのどのテーマと最も強く結びついているか」を軸に考えることが重要です。外部環境は全企業に同じように作用するわけではなく、事業の形態やビジネスモデルによって影響の受け方は大きく異なります。テーマごとの負荷や追い風の強弱が、そのまま2026年の成長スピードの差につながり、準備の深さが競争力を左右する年になると考えられます。
2026年の市場を読むための実務視点

2026年の市場は、景況DIの“揺れ”がそのまま業界ごとの動きに表れやすい一年になります。とくに、採用難、物価、金利、消費動向、設備投資といった外的要因が業種別に異なる形で作用し、同じ景気環境でも「伸びる企業」と「踏ん張りが必要な企業」がはっきり分かれる可能性があります。
そこで、主要な業種ごとに想定される動きを整理すると、次のようなポイントが見えてきます。
・小売・飲食・サービス
個人消費の伸びが鈍く、客単価や回転率が鍵になります。採用難が続くため、スタッフ定着がそのまま業績に直結します。価格の見直しや付加価値づくり、省人化の取り組みが必要です。
・物流・運輸
人手不足の影響がもっとも強く出やすい分野で、賃上げ圧力が続きます。燃料費や金利の動きにも左右されやすく、業務効率化やルート管理の最適化が欠かせません。中長期では設備更新が大きなテーマになります。
・建設
資材価格は高止まりが続き、案件の進捗もエリアによって差が出ます。人材確保が難しい状況の中で、2026年は採算管理の精度が求められます。公共工事の動きや金利の方向性が直接影響します。
・製造業
円安や部材価格の落ち着きが追い風になる一方、投資判断は企業ごとに分かれます。輸出企業と内需企業で明暗が出やすく、生産性向上のための設備投資や省力化の計画が焦点になります。
・IT・デジタル領域
人材需要が高く、DX領域は引き続き伸びる見込みです。採用難が強い一方で、外注やツール導入による効率化ニーズが高まります。中小企業のデジタル投資が増え、商機が広がる可能性があります。
・資金繰り・金融面の動き(全業種共通)
金利の影響が続き、資金調達の選択肢を複数持つ必要が高まります。融資の見直し、支払い条件の最適化、ファクタリングの活用など、キャッシュフロー管理の重要度がさらに強まる一年になります。
こうした動きを踏まえると、2026年の市場では「業界全体の傾向」よりも「自社の立ち位置」を把握することが重要になります。同じ景況感でも、業種やビジネスモデルによって影響の受け方がまったく異なるため、何が自社の強みで何がリスクになるのかをより細かく見ていく必要があります。
経営者が押さえておきたい5つのアクション
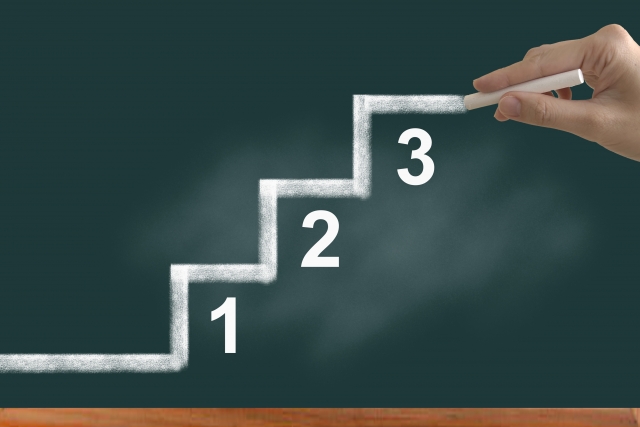
市場の揺らぎが大きい局面では、外部環境の変化を正確に読むよりも、変化に耐えられる経営の“軸”を持つことが重要になります。2026年は、業種ごとの差が広がる一方で、企業の判断スピードや準備の深さが業績に直結しやすい一年です。
景況DIの動きと市場の主要テーマを踏まえ、2026年に向けて意識しておきたい実務的なアクションを整理すると、以下の5つが柱になります。
① コスト構造を見直し、収益の“形”を整える
原材料費や人件費の増加が続く中、従来の前提で経営を行うことは難しくなっています。固定費と変動費のバランスを見直し、価格転嫁だけでなく収益構造そのものの改善に取り組むことで、環境変動に耐えられる体制が整います。
② 新規採用より“定着率”を優先する
採用難が続く中、人材の確保には限界があります。教育の仕組み、働きやすい環境整備、評価の透明性など、離職を防ぐ仕組みを整えることで、業務品質の安定と採用コストの削減につながります。
③ 省力化・効率化への投資を選択的に進める
全てを自動化する必要はありませんが、業務負荷が集中している部分を優先的に効率化するだけでも、現場の負担は大きく減ります。DXや設備投資は助成金と組み合わせることで負担を抑えられ、長期の収益改善につながりやすくなります。
④ 資金調達の選択肢を広げ、資金繰りを安定させる
金利の影響を受けやすい局面では、借入一本に依存する体制はリスクになります。複数の資金調達手段を持ち、支払い条件の最適化や売掛金の早期回収など、資金の流れそのものを見直すことで、外部環境に左右されにくい資金繰りが実現します。
⑤ 価格と提供価値のバランスを見直す
単純な値上げでは顧客離れのリスクがあります。どの部分に付加価値を置き、どこを効率化するのかを明確にし、「選ばれる理由」をつくることが2026年の競争力につながります。価格戦略とサービス品質の再定義は欠かせない視点です。
これらのアクションは華やかな施策ではありませんが、外部環境の揺れが大きい時期ほど効果を発揮します。変化を予測するのではなく、変化に備えた経営基盤を整えることが、2026年の市場で安定した判断を行うための鍵になります。
2026年、市場の波をどう読むか

ここまで見てきたように、2026年の市場は特定の方向へ一斉に動くのではなく、業種や事業モデルごとに“異なる波”が訪れやすい一年になります。景況DIの揺れが示しているのは、景況感がプラスかマイナスかよりも、その上下が「どの業界で」「どの程度の強さで」起きるかという点です。
景況DIは景気の未来を断言する指標ではありませんが、変化の入口をとらえるには十分な手がかりがあります。数値の上下よりも、その背後にある企業心理や投資姿勢の変化を読むことで、自社にとっての“影響の方向”が見えやすくなります。
2026年の市場を読み解くうえで重要なのは、景況DIを単体で追うのではなく、前章で整理したテーマ――採用難、物価と金利、省力化投資、個人消費、為替といった複数の要素と組み合わせて考えることです。これらのテーマがどの順番で、どの強さで自社に影響しやすいかを把握しておくことで、変化を“読む”のではなく、“備える”姿勢に近づきます。
とくに2026年は、準備の深さが企業ごとの成長スピードに表れやすい環境になります。市場全体の数字が良くても、自社の業界が追い風とは限りません。逆に全体の数字が伸び悩んでも、自社の強みが活きる分野では十分に成長の余地があります。
つまり、2026年の市場を読むということは、外部環境の予測ではなく、自社の立ち位置と強みを再確認する作業に近いと言えます。景況DIはその判断材料のひとつとして、先行きの変化に気づく“センサー”の役割を果たします。市場の波は必ずしも揃って動くわけではありません。その波をどう捉え、どう乗りこなすかが来年の経営に直結します。
🔑 本章のまとめ
2026年の市場は、一方向ではなく複数の波が重なり合う環境になります。景況DIが示す“ばらつき”は、業界ごとに異なる動きが強まりやすいサインです。重要なのは変化を正確に当てることではなく、自社に影響しやすいテーマを見極め、備える体制を整えておくことです。採用、人件費、金利、消費動向、効率化投資といった要素を組み合わせて読み解くことで、2026年の判断軸がより明確になります。






